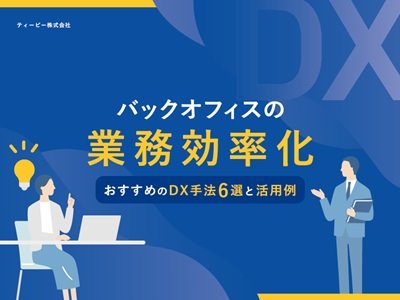バックオフィス業務の改善にAIを活用するメリット【総務・人事・経理必見】
最終更新日:2025年03月26日

そこで本記事では、総務、経理、人事などのバックオフィスでのAI活用に役立つ情報をまとめました。自社のバックオフィス業務に課題を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
【おすすめ資料】
バックオフィスの業務効率化 おすすめのDX手法6選と活用例
- バックオフィス業務の改善にAIを活用するメリット
- 重要な業務にリソースが割けるようになる
- 業務の正確性が向上する
- コスト削減につながる
- 業務の属人化が解消しやすい
- 従業員の満足度が向上しやすい
- バックオフィスが抱える現状の問題点
- 未だにアナログでの作業が多い
- 業務が属人化しやすい
- 人的ミスが発生しやすい
- 閑散期・繁忙期の差が激しく人材の確保が難しい
- バックオフィス業務にAIを取り入れる具体的な方法
- ChatGPTなどの生成AI
- RPA
- チャットボット
- バックオフィス業務でAIを活用する前に注意すべきこと
- 業務プロセスの見直しが必要になる
- 従業員のAIリテラシーを向上させる
- 生成AIを活用する際はファクトチェックをおこなう
- AI活用後は定期的に評価・分析をおこなう
- まとめ
バックオフィス業務の改善にAIを活用するメリット
AIの適切な活用は、総務、経理、人事などのバックオフィス業務にさまざまなメリットをもたらします。まずは、バックオフィス業務にAIを活用することで得られる主なメリットを紹介します。
重要な業務にリソースが割けるようになる
総務や経理、人事などでは、日々さまざまな書類の作成や会計処理がおこなわれていますが、その中にはAIによって自動化できる作業が少なからず存在します。たとえば、勤怠管理や人事評価、給与計算や帳簿の処理、請求書の発行などが自動化できれば、それらにかけている時間を大幅に圧縮できます。それにより、ほかの業務に時間を割けるようになり、業務の生産性向上に役立ちます。
業務の正確性が向上する
バックオフィスではさまざまな入力作業がありますが、業務の多忙さもあって入力ミスや転記ミス、集計ミスなどが起きがちです。一方、AIを使って業務の自動化を進めれば、人的なミスを削減できます。AIによってミスが減り、作業負担も軽減されれば、業務への集中力が高まるメリットも期待できます。
コスト削減につながる
AIによってバックオフィスの作業を自動化すれば、対応する従業員の数を減らすことが可能です。仮に人員削減には至らないとしても、残業を減らすことなどでコスト削減が見込めます。
また、AIによってミスが減れば、従来トラブル対応に充てていた時間が不要になります。たとえば、顧客に宛てた書類にミスがあると、担当者レベルでは済まないこともあり、多くの時間的コストを無駄にします。また、お金のやり取りに関する間違いも多方面にダメージを与えることが多いので、これらのミスを減らすこと自体がコスト削減に貢献します。
業務の属人化が解消しやすい
総務や人事、経理では専門性を要する業務もあるため、特定の人にしかできない作業が発生しがちです。そのように業務の属人化が進むと、担当者が病欠・退職などした際に業務に支障が出ることもあるので、企業として健全な状態とはいえません。AIを適切に導入し、業務の自動化やナレッジベース構築による業務標準化を進めることで、属人化の解消が図れます。
従業員の満足度が向上しやすい
バックオフィスでは煩雑な仕事に追われることが多く、従業員のモチベーションが低下することもあります。ストレス過多な状態が慢性化すると、職場の雰囲気が暗くなり、従業員が頻繁に辞めることも考えられます。AIの適切な活用が進めば、日々のストレスが減って従業員の満足度向上につながります。
バックオフィスが抱える現状の問題点
多くの企業では、バックオフィス業務において次のような問題点が見受けられます。
- 未だにアナログでの作業が多い
- 業務が属人化しやすい
- 人的ミスが発生しやすい
- 閑散期・繁忙期の差が激しく人材の確保が難しい
以下、それぞれ詳しく解説します。
未だにアナログでの作業が多い
多くの企業において、販売や営業などのフロントオフィスはデジタルツールが導入されやすいですが、バックオフィスのデジタル化は後回しにされがちです。そのため、総務や人事、経理などでは紙の資料を管理するなど、アナログ作業が多い傾向が見られます。
紙の書類は保管するにも場所を取る上、必要に応じて運んだり持ってきたりする手間も生じます。また、同時作業がしにくく、上司や関係部署に回覧する際もデジタルデータより時間を要します。
さらに、アナログ資料が多い職場ではリモートワークも難しいので、働き方が限定される欠点もあります。
業務が属人化しやすい
バックオフィスの業務は、製造工程などに比べてマニュアル化されにくく、人手不足などもあって効率化が進みにくい傾向が見られます。そのため属人化に陥りやすく、特定の人しか扱えない状態が起きがちです。
業務が属人化すると、特定の人に負担がかかるため、その人のモチベーション低下が懸念されます。また、特定のスキルを持つ人が休んだだけで業務に支障が出ることもあるので、企業としては大きな問題です。
人的ミスが発生しやすい
アナログ作業は人の手でおこなわれるため、人的ミスが発生しがちです。特に、先述したようにバックオフィス業務が属人化している場合、作業者への負担がより大きくなるため、疲労による集中力の低下からミスの発生を誘発しかねません。
人的ミスが生じやすい状態では、修正のために余計な時間を取られたり、周囲の人や取引先に迷惑をかけたりするリスクも高まります。
閑散期・繁忙期の差が激しく人材の確保が難しい
バックオフィスでは、閑散期と繁忙期で必要な人員数に差が生じがちです。たとえば月末や月初、決算時期や年度替わりの時期などには、多忙を極める状態になることがあります。しかし、繁忙期に合わせて人を確保すると、閑散期にリソースが無駄になってしまいます。そもそもバックオフィス業務は売上に直結しない都合、売上に直接関与する部門よりも人員確保が後回しになりがちです。
そのため、繁忙期に心身が疲弊しやすい上、繁忙期が近づくだけでストレスを感じる人もいます。このような状態では、従業員の満足度が上がらず、結果的に企業としてのマイナスにつながります。
バックオフィス業務にAIを取り入れる具体的な方法
ひと口にAIといってもさまざまな種類があり、それぞれ適性や特長が異なります。そのため、事前に適切な知識を得て、自社に適した形で導入することが大切です。バックオフィスにAIを取り入れる方法には、以下のようなものが挙げられます。
- ChatGPTなどの生成AI
- RPA
- チャットボット
ChatGPTなどの生成AI
近年、さまざまな場所で取り入れられているのが、ChatGPTなどをはじめとする生成AIです。生成AIは、学習したデータから新たなコンテンツを生成することを目的に開発されています。たとえば、文章の要約や生成、翻訳などに役立つほか、画像や音楽の編集や生成などにも利用できます。人事や総務、経理などのバックオフィスにおいても、以下のような幅広い用途に使用可能です。
- データ分析
- 各種書類作成
- メール文書の作成
- 議事録の作成
- 業務マニュアル作成
- 表計算の関数作成
- 社内向けFAQ作成
上記の業務に生成AIを取り入れることで、人的ミスの防止や作業の効率化、コスト低減や人的リソースの適正化が期待できます。
一方で、生成AIが作り出す文書にも誤りはあるため、チェック工程は欠かせません。この点は、のちほど詳しく解説します。
RPA
RPA(Robotic Process Automation)は、ロボットを用いて業務を自動化することを意味します。工場の生産ラインなどで用いられる物理的動作をするロボットを使ったRPAもありますが、ここではソフトウェアを用いて業務効率化をおこなうバックオフィス向けのRPAについて解説します。
RPAを用いたオフィスの効率化は、業務の生産性向上を支える手段として注目を集めており、総務省も働き方改革の一環として取り上げています。RPAを導入することで、これまで手作業で行われていたデータ入力や処理、報告書作成といった反復的な業務を自動化できます。また、異なるアプリケーション間でのデータ連携や統合もスムーズに行えるため、社内データの分析や整理が効率的に進められます。
参照:RPA(働き方改革:業務自動化による生産性向上)|総務省
また、上記以外にも経理上の仕訳や人事考課、POSデータの集約や経費の精算、社内の資産管理など、多くの用途に利用可能です。
RPAは、一定の法則に沿っておこなう業務の自動化に向いているため、ルールや慣習が重視されるバックオフィス業務との相性に優れるとされています。バックオフィスにRPAを導入することで、業務効率の向上や人件費の削減、人的ミスの抑止や作業品質のアップ、従業員の満足度向上や意識改革を促せるといったメリットが得られます。
チャットボット
チャットボットとは、「Chat(会話)」と「Robot(ロボット)」という2単語からなる造語です。一般的には、質問に対して用意した回答を返す「シナリオ型」と、AIを使って複雑な質問にも対応できる「AI型」があります。カスタマーサポートなどで利用されることもありますが、ここでは従業員の質問に答えるチャットボットについて解説します。
従業員からの問い合わせにチャットボットを導入すると、それまで従業員の質問を受けていたオペレーターの負荷を軽減できます。企業内では上下関係があり、時には強い言葉を発する人もいるので、対人のやり取りにはストレスが生じがちです。そのため、チャットボットは総務部門などで働く人の満足度向上に寄与します。
また、チャットボットで対応した問い合わせのログを分析することで、従業員が抱えがちな悩みを把握できます。さらに、チャットボットなら24時間対応できるので、問い合わせをする側としても、時間を選ばず質問できるメリットがあります。特に飲食業や輸送業など、バックオフィスの従業員が勤務していない時間にも稼働している業種では、チャットボットの有効性が高まります。
さらに、問い合わせ対応の属人化も防止できるので、チャットボットの活用はバックオフィスの生産性向上にも有効です。
バックオフィス業務でAIを活用する前に注意すべきこと
経理や総務、人事や法務などのバックオフィスでAIを活用する際には、いくつか注意すべき点が存在します。主な注意点としては、以下が挙げられます。
- 業務プロセスの見直しが必要になる
- 従業員のAIリテラシーを向上させる
- 生成AIを活用する際はファクトチェックをおこなう
- AI活用後は定期的に評価・分析をおこなう
業務プロセスの見直しが必要になる
バックオフィスでのAI活用を検討する上で欠かせないのが、業務プロセスの見直しです。日常業務の流れを洗い出して、所要時間や関わる人員を把握し、現状の問題点や良好な点などを踏まえておかないと適切なAI活用はできません。
そのため、まず導入部署や関係部門の業務の棚卸しをおこない、ワークフローを整理することから始めましょう。また、実際に作業している人の意見を聞き、現場の実情を把握することも重要です。それらの工程を経て業務を可視化し、どの部分でAIを活用するべきか、人が対応すべき部分はどこかなどを検討してから、導入計画を進めることをおすすめします。
従業員のAIリテラシーを向上させる
AIを十分に活用するには、従業員のAIに対する理解を深めることが不可欠です。
AIは、適切に利用すればさまざまなメリットをもたらしますが、決して万能ではありません。使い方によっては、想定したメリットを享受できない可能性もあります。AIができることやできないこと、有効な使い方や不適切な使い方などを研修などで周知しましょう。
また、AIを実際に使う従業員には、問題なく使用できるようにトレーニングを提供する必要があります。AIの使用に関するマニュアルやガイドラインの整備も必須です。
生成AIを活用する際はファクトチェックをおこなう
ChatGPTをはじめとした生成AIは多数のデータから文章などを生成できる一方で、誤った内容をアウトプットすることもあるため、生成された文書のファクトチェックが欠かせません。文書の重要度が上がるほど、その必要性は増します。
誤った内容の文書が顧客やサプライヤーなどに流れると、訂正やお詫びなど事態の収拾に手間をかけることになります。そのため、生成AIを活用する場合は、ファクトチェックの過程を組み込んでもなお効率化が望める業務への利用に留めるなど、使い方をしっかり考えましょう。
AI活用後は定期的に評価・分析をおこなう
バックオフィスに限らず、業務にAIなどの新しいツールを導入したあとには、定期的に評価・分析をおこないましょう。
評価・分析をおこなう上では、AI活用によってどの程度の効率化やミスの削減などが得られたかなど、定量的に情報収集することが重要です。結果をフィードバックし、そこから得た知見をもとにさらなる改善を進めることで、 AIの導入効果の最大化が図れます。
特に重視すべきなのはROI(投資利益率)です。AIの導入にかけた費用と得られた利益を比較することで、AI活用の成果を判断できます。
まとめ
企業のバックオフィスはデジタル化の途上にあることが多く、しばしば属人化や人手不足などの問題が見られます。AIを活用することで、バックオフィス業務の効率化やコスト削減、属人化の解消、従業員満足度の向上といったメリットが期待できます。
とはいえ、それらメリットを十分に享受するには、適切な形での導入が欠かせません。AI活用の正しい知識やリテラシーを身につけることが、AIの導入効果を高めるためには重要です。
●詳しい解説資料のダウンロードはこちらから
バックオフィスの業務効率化 おすすめのDX手法6選と活用例