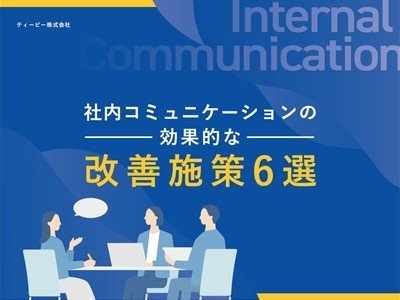1on1ミーティングは意味ない?失敗例や注意点、実施のポイントを解説
最終更新日:2025年05月26日

【おすすめ資料】
社内コミュニケーションの効果的な改善施策6選
- 1on1ミーティングが「意味ない」と言われる理由
- 時間や工数が無駄に感じる
- 話すことがなく必要性を感じていない
- 業務改善や人材育成につながっていない
- 上司と部下の溝が深まる懸念がある
- 1on1ミーティングの失敗例
- 1on1ミーティングを実施する目的が明確化されていない
- 上司の一方的なコミュニケーションになっている
- 業務の話題が中心となってしまいがち
- 前回の話を忘れていることがある
- 有意義な1on1ミーティングを実施するためのポイント
- 実施の目的を明確化して社員に共有する
- 毎回話すテーマを決めて実行する
- ミーティングの時間を短めに設定する
- 人材育成の観点を持って実施する
- 中長期的な視点を持って全社的に取り組む
- トークログを残して実施を継続する
- 部下が話しやすいように会話のテクニックを身につける
- 1on1ミーティングを実施する際の注意点
- 高圧的な態度をとらない
- プライバシーを侵害しない
- 一方的に批判や指示をしない
- まとめ
1on1ミーティングが「意味ない」と言われる理由
1on1ミーティングは、上司と社員(部下)のコミュニケーションを深めるためにおこなわれますが、「意味ない」と言われる背景には以下のような理由があります。
- 時間や工数が無駄に感じる
- 話すことがなく必要性を感じていない
- 業務改善や人材育成につながっていない
- 上司と部下の溝が深まる懸念がある
時間や工数が無駄に感じる
1on1ミーティングは、業務時間を割いて定期的に実施されます。内容の重複や既知の情報の再確認に終始すると、有意義な時間を過ごせず、その分重要な業務に遅れが生じる可能性もあり、ただ時間を浪費するだけと感じるのも仕方がありません。
また、日程調整や場所の確保、テーマ・内容の決定など実施までの準備が必要です。定期的に実施される1on1のための工数が手間となり、上司と部下双方にとって負担やストレスの種となることが考えられます。
話すことがなく必要性を感じていない
回数を重ねるごとに話題が尽き、話す内容がなくなることがあります。最初は業務関連について話せますが、特に問題がない場合、上司に時間を確保してもらうことに対してプレッシャーを感じる部下もいます。
上司側も、どう対応すべきか戸惑ってしまい、結果的に雑談だけで終わってしまうことも。このような状態では、1on1ミーティングを効果的に活用できず、目的を達成することも難しいです。
業務改善や人材育成につながっていない
上司に対して悩みや不安などを本音で話せない部下もいます。せっかくの1on1ミーティングが当たり障りのない会話で終わってしまったら、問題が把握できず、業務への課題も明確化できません。
そのため、人材育成や業務改善、といった1on1を実施する意義が薄れてしまいます。さらに、これが定期的に続くと本来の目的から外れた施策になってしまう可能性もあるため注意が必要です。
上司と部下の溝が深まる懸念がある
1on1ミーティングは、上司と部下間の円滑なコミュニケーションを促進するために実施されますが、会話の中身や目的を誤ると逆効果になる懸念があります。
特に上司と部下の考え方や意見、価値観が異なる場合、不満や不信感を生み出す原因になり、信頼関係を築くのが困難となります。加えて、上司が以前の1on1で話した内容を忘れていたり、問題について真剣に捉えていないと感じたりすると、関係性が悪化する原因になります。
1on1ミーティングの失敗例
具体的な失敗例は以下のようなものが挙げられます。
- 1on1ミーティングを実施する目的が明確化されていない
- 上司の一方的なコミュニケーションになっている
- 業務の話題が中心となってしまいがち
- 前回の話を忘れていることがある
1on1ミーティングを実施する目的が明確化されていない
目的が双方に共有されていないまま実施されているケースがあります。「なぜ実施するのか」「企業として1on1をどう活かすのか」が明確でなければ、部下が漠然と上司の質問に答えるだけの時間となってしまい、有意義な議論が生まれず効果も実感しにくくなるでしょう。
また、経営層と中間管理職の間に1on1ミーティングの目的についての認識のズレが生じる場合もあります。たとえば、離職率の低下を目的とするのか、業務目標の達成を目指すのかといったものです。上層部と現場の間での認識のすり合わせが不足していることで、話す内容や引き出す意見、取り組む姿勢などに齟齬が生じることもあります。
上司の一方的なコミュニケーションになっている
対話が基本である1on1ミーティングの場でも、上司が一方的に話して終わるケースは少なくありません。このような状況では、上司は部下の悩みに共感できず、部下の率直な意見を引き出すのも難しいです。部下にとって、上司と2人で話す1on1は緊張感がある場なので、基本的には上司が話しやすい雰囲気を作り、安心して本音で話せるよう促すことが求められます。
業務の話題が中心となってしまいがち
1on1ミーティングは、部下をサポートする場であるべきです。業務の進捗や設定した目標の確認のみで終わると、部下が抱えている悩みに十分に向き合えず、表面的な関係にとどまってしまいます。
部下が日常的に感じている不安や悩みに耳を傾け、それに対する適切なアドバイスをするのが上司の役割です。たとえば、目標を達成できなかった理由を一緒に確認したり、業務以外の話題でコミュニケーションをとったりするなど柔軟な対応が求められます。キャリアに関するアドバイスや雑談を交えつつ、限られた時間を有効に使う必要があります。
前回の話を忘れていることがある
日々忙しい業務に追われていても、上司が前回の1on1ミーティングで話した内容を覚えていないと、部下にとって不信感の原因となります。同じ質問や話題を何度も繰り返したり、一貫したアドバイスができなかったりすると、時間の無駄と感じて、仕事に対するモチベーションも下がってしまうことが懸念されます。
1on1は継続しておこなうのが基本です。上司が毎回のミーティングの内容を把握して、適切なフィードバックやアドバイスをすることで、部下は自分の意見が重要視されていると感じ、ミーティングに対しての意欲が高まる効果があります。
有意義な1on1ミーティングを実施するためのポイント
目的を達成するための1on1ミーティングを実施するための7つのポイントを挙げ、それぞれ解説します。
- 実施の目的を明確化して社員に共有する
- 毎回話すテーマを決めて実行する
- ミーティングの時間を短めに設定する
- 人材育成の観点を持って実施する
- 中長期的な視点を持って全社的に取り組む
- トークログを残して実施を継続する
- 部下が話しやすいように会話のテクニックを身につける
実施の目的を明確化して社員に共有する
上司と部下の双方が「なぜ1on1ミーティングが必要なのか」を把握しておくことが非常に重要です。そのためには、目的を明確にして共有する必要があります。
目的が曖昧だと、単なる業務報告や雑談で終わり、有意義な対話を重ねることができません。お互いにとって価値ある時間を過ごせれば、部下は1on1を肯定的に捉え、普段の行動に好影響を与えます。また、共通の目的を達成するためのモチベーションも上がり、主体的な行動を促すきっかけにもなります。
毎回話すテーマを決めて実行する
目的に応じたテーマを事前に設定し、それに沿って進めることが重要です。これにより、話題不足で困ることがなく、無駄な時間となってしまう事態を防げます。
上司側だけでなく、部下にテーマを決めてもらうのがおすすめです。難しい場合は、慣れるまで人事部などからテーマを提示してもらう方法もあります。お互いにテーマを決め、あらかじめアジェンダで共有しておけば、部下も話す内容を考えやすくなります。テーマに沿って進めれば、双方が同じ目標に向かい、議論も深まり、効率的な1on1ミーティングの実施につながります。
ミーティングの時間を短めに設定する
1on1ミーティングは、1回の所要時間を短めに設定するのが効果的です。部下にとって、上司と2人きりの長時間のミーティングは苦痛と感じやすく、集中力が持続しないこともあります。たとえば、週1回30分程度であれば、ストレスを感じることなく継続しやすいです。
短時間・高頻度で実施すれば、お互いの考え方を頻繁に共有できます。また、定期的な実施により、適切な時間を確保でき、回を重ねるごとにお互いの心理的な距離が縮まり、信頼関係を築きやすくなります。1回でも機会を失うと、それに慣れてしまう可能性もあるので、キャンセルせざるを得ない場合は再調整し、いったん決めたサイクルを守るのが重要です。
人材育成の観点を持って実施する
1on1ミーティングで上司がティーチングに終始し、部下は指示を受けるだけで成長につながらないケースがあります。ティーチングは、未知の知識を教える指示型のコミュニケーションで、業務上の手続きなどを教えるために役立つ手法です。
1on1といった部下の成長を目的としたコミュニケーションを重視する場においては「コーチング」や「フィードバック」が適しています。これらは、自らで解決法を見出せるよう導いたり、改善点を伝えたりする方法で、思考を促し成長をサポートします。1on1が、単なる報告の場にとどまらず、部下のスキルアップにつながるよう、上司にも最適なスキルを身につけることが求められます。
中長期的な視点を持って全社的に取り組む
部下が成長するスピードは、個人差があります。短期間の実施では成果が現れにくいため、1on1ミーティングは中長期的に取り組みます。早急な結果を求めると、うまく会話が進まない、双方がスキル不足を責めるといった苦痛が生じ、継続できなくなる可能性もあります。
中長期的に取り組むには、現場だけではなく、問い合わせ窓口の設置や1on1に関するスキルアップ研修など、包括的なサポート体制を整えるのが効果的です。また、定期的にアンケートをおこなうなど、改善を図る努力も必要です。
トークログを残して実施を継続する
1on1ミーティングの際にトークログを残せば、過去の議論を簡単に確認できるため、課題の解決や進歩の確認に役立ちます。メモも有効ですが、実施記録やトークログ、スケジュール管理ができるツールを活用すれば、定期的な実施が容易になり、目標も達成しやすくなります。
エクセルのようなソフトでも可能ですが、データが増え続けると管理しきれなくなる可能性があるため、専用ツールの使用がおすすめです。管理ツールで情報を整理して、重要な事柄や進歩を一元管理すれば、上司と部下間で共通の認識を持ちやすくなり、より効果的な1on1の実施につながります。
部下が話しやすいように会話のテクニックを身につける
部下が上司に気を使うのは当然です。それを踏まえて、上司は1on1ミーティングで部下の本音が引き出せるような会話テクニックを身につける必要があります。
効果的なのは、回答に制約を設けないオープンクエスチョン(「どう思いますか?」「どんな点で困っていますか?」)や、回答に制約があるクローズドクエスチョン(「はい・いいえの2択」「A・B・Cの3択」)といった会話テクニックです。前者は、部下から意見や情報を話してほしい場合に、後者は部下の意見を明確に知りたい場合に有効です。これらをうまく使い分けることで、1on1の質が向上します。
1on1ミーティングを実施する際の注意点
最後に、効果的な1on1ミーティングを達成するための注意点をチェックしてみましょう。
- 高圧的な態度をとらない
- プライバシーを侵害しない
- 一方的に批判や指示をしない
高圧的な態度をとらない
1on1ミーティングの場で、上司が部下に高圧的な態度をとるのは御法度です。部下の話を遮ったり、全否定したりすると、萎縮して話しにくくなります。1on1では、上司として積極的に意見を伝えたい気持ちを抑えて、部下が自主的に発言できる場にする配慮が必要です。
上司が共感を示す姿勢を見せれば、部下が話しやすい雰囲気を作れます。サポートする立場を保ちながら、対話を通じて上司と部下の信頼関係を深めることが効果的で有意義な1on1のキーポイントです。
プライバシーを侵害しない
上司が部下に対して過剰に個人的な質問をしたり、プライベートな領域に踏み込んだりするのは避けるべきです。業務とは無関係な私生活について強引に聞き出そうとすると、部下は不快に感じて信頼関係が損なわれる恐れがあります。たとえ関係性が良好であっても、プライバシーを侵害しない程度の距離感を保つのがポイントです。
緊張をほぐすために雑談で話しやすい雰囲気を作ることは有効ですが、過度に親しくなる必要はなく、上司と部下という関係を維持したまま、安心して話せる環境を整えると1on1が効果的に機能します。
一方的に批判や指示をしない
1on1ミーティングは、上司が一方的に部下の批判や否定をする場ではありません。部下の話を無視したり、主観的な意見を押し付けたりすると、コミュニケーションの障壁になります。たとえば、部下は勇気を出して提案したアイデアを一方的に否定されたら、モチベーションが低下し、自己表現しにくくなります。
部下が話題に困った場合は上司がサポートする必要がありますが、そうでなければ基本的に部下が話したい話題を優先すべきです。部下の話に耳を傾け、共感を示し、建設的にフィードバックするなど、適切なアドバイスをすることで信頼関係が深まり、意味のある1on1が実現します。
まとめ
1on1ミーティングは、単なる上司と部下がコミュニケーションを図る場ではありません。明確な目的のもと、中長期的な視点を持って対話して課題を乗り越えるアイデアや気づきを積み上げていくことが重要です。これにより「意味ない1on1」から、「有意義かつ目的を達成できる1on1」へと変化していくはずです。
そのためには、上司のスキルアップや管理ツールの活用など、さまざまな取り組みが必要です。本記事で紹介した失敗例や注意すべきポイントを参考にして、効果的な1on1ミーティングを実施し、企業全体のパフォーマンス向上に役立ててください。
●課題解決に役立つ資料のダウンロードはこちらから
社内コミュニケーションの効果的な改善施策6選