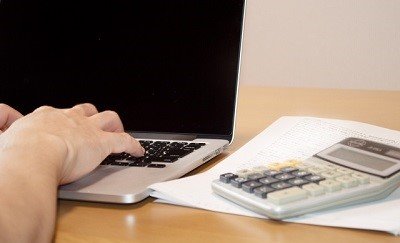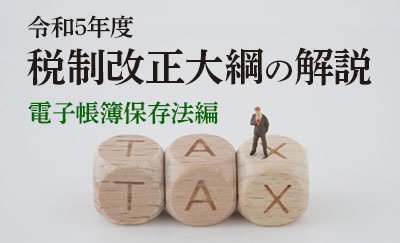発行したインボイスについても保存が必要ってご存知ですか?
最終更新日:2024年02月22日
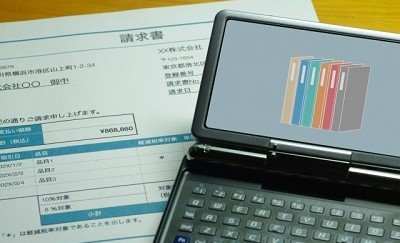
インボイス制度開始前後での取扱いの違い
インボイス制度が始まるまでは保存義務はない?
インボイス制度が始まると仕入税額控除の要件として受け取ったインボイスの保存が必要となりますが、それだけではなく、売手として発行するインボイスの控えについても保存する必要があります。
実はインボイス制度が始まるまでは、消費税法のどこにも
「請求書等の控えを保存しておきなさい」
とは書いてありません。
インボイス制度の開始とともに、インボイス発行事業者には発行したインボイスの控えなどを保存する義務が生じるのです。
法律上の義務として明記されるとはいっても、取引先から問合せが来たときに必要となることなどから、ほとんどの事業者は発行した請求書等を現在でもきちんと保存しているでしょう。
そういう意味では保存すること自体は事業者にとって大きな負担にならないと考えられます。
控えの保存期間は?
保存義務と聞いて皆さんが気になるのは
「いつまで保存しておく必要があるのか?」
という点ではないでしょうか。
保存期間としては
「交付した日等の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間」
とされています。
ちょっとわかりにくい書き方になっていますので、具体例で確認しておきましょう。
例として3月決算の会社で2024年3月期について確認します。
・課税期間の末日の翌日→課税期間の末日(2024年3月31日)の翌日なので2024年4月1日
・2月を経過した日→2024年6月1日になります
つまり、2024年6月1日から7年間の保存が必要となりますので保存期限は2031年5月31日です。2031年3月31日が期限ではありませんのでご注意ください。
発行したインボイスの具体的な保存方法
発行したインボイスの控えなどを保存する際には、法律上どのような要件が求められているでしょうか?
法律に書いてあるのは
・整理して保存する
・法律で定められた期間(7年間)保存する
・納税地に保存する
の3点だけです。
「このようにファイリングしなさい」「こんな形式で保存しなさい」といったことは何も決められていません。
一般的な保存方法としては、たとえば請求書をインボイスとするのであれば、取引先に送付する請求書を印刷する際に控えも一緒に印刷して、その控えをファイリングするという方法が考えられます。
作成するインボイスが月に10~20枚程度であればこの方法でも問題無く対応できるかもしれませんが、月に100枚以上請求書を発行するような事業者だと紙代や保管場所の負担が大きくなります。
また、小売店などで店頭にてお客様にインボイス対応したレシートを渡している場合はどうでしょうか?
お客様に発行すると同時にもう1枚レシートを発行してかつそれを保存しておくのは結構大変な作業です。
こうした事情に配慮して、国税庁が公表しているインボイスQ&A問76では、実際に発行したインボイスそのもののコピーに限らず、インボイスの記載事項が確認できるレベルの記載があるものでもよいとしています。
具体例として
・簡易インボイスの場合のレジのジャーナル
・インボイスの記載事項を確認できる一覧表や明細表
が挙げられています。
つまり請求書ソフトなどから「請求書一覧表」といったリストを出力できて、そのリストでインボイスに必要な記載事項である
- インボイス発行事業者の名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減対象資産の譲渡等である場合はその旨を含む)
- 税率ごとの取引金額合計額(税抜or税込)と適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 取引先の名称
インボイスをデータで保存する際の注意点
インボイスはデータで渡すことも認められていますので、データのまま保存することも考えられます。
発行したインボイスの控えなどをデータで保存するケースとしては2つあります。
【ケース1】取引先にインボイスをデータで渡した場合
【ケース2】請求書ソフトなどでインボイスを作成したが取引先には紙で渡した場合
それぞれのケースについて注意すべき点は以下の通りです。
【ケース1】の注意点
このケースは電子帳簿保存法における「電子取引」に該当します。
そのため「電子取引」を保存する際のルールを守ってインボイスデータを保存しなければなりません。
「電子取引」を保存する際のルールは次のとおりです。
- システム概要書等の備え付けを行うこと
- パソコン・モニター・プリンター及び操作説明書を備え付けて、わかりやすい状態ですぐに確認できるようにしておくこと
- 次のような検索をできるようにしておくこと(ダウンロードの要請に応じる場合は(イ)(ウ)は不要) (ア)取引年月日・取引金額・取引先で検索できる
- 以下のいずれかの措置を行うこと (ア)発行側がデータにタイプスタンプを付す
(イ)日付・金額については範囲指定できる
(ウ)2以上の条件で検索できる
(イ)受取側が取引データ受領後に自社でタイムスタンプを付す
(ウ)訂正削除履歴が残る又は訂正削除不可のソフトに保存する
(エ)訂正・削除に関する事務処理規程を備え付けて運用する
なお電子帳簿保存法では「電子取引」についてはデータのまま保存する義務がありますが、消費税法においては印刷して紙で保存することも認められています。
この場合、電子帳簿保存法には違反しているけれども消費税法には違反していないというスッキリしない状況になりますので、インボイスをデータで取引先に渡した場合にはデータで保存しておくようにしましょう。
【ケース2】の注意点
このケースでは取引先にデータを渡していませんので「電子取引」には該当しません。
その一方で
「せっかくExcelファイルや請求書ソフトなどの中にデータがあるのだから、わざわざ保存用に控えを印刷せずにデータのまま保存したい」
と考える方もいるのではないでしょうか。
これについてはインボイスデータを最初から最後まで一貫してデータでつくっているのであれば、データのまま保存しておくことも可能です。
この場合は電子帳簿保存法の「電子書類」に該当しますので、「電子書類」の保存ルールに従って保存します。
なお「電子書類」の保存については「電子取引」と異なり義務ではありません。発行したインボイスの控えは紙で保存したい方は紙で保存しましょう。
「電子書類」の保存にあたっては以下のルールを守る必要があります。
- システム概要書等の備え付けを行うこと
- パソコン・モニター・プリンター及び操作説明書を備え付けて、わかりやすい状態ですぐに確認できるようにしておくこと
- 次のような検索をできるようにしておくこと(ダウンロード要請に応じる場合は(ア)(イ)ともに不要) (ア)取引年月日等の日付で検索できる
(イ)日付については範囲指定できる
「電子取引」よりルールは少ないですが、データで保存する際にはこれらのルールに従って保存しましょう。
関連記事:電子帳簿保存法とは?2024年からの改正内容や対象書類、保存要件を解説
執筆者情報
加藤博己税理士事務所 所長 加藤博己(税理士・ファイナンシャルプランナー)税理士でありながらその枠にとどまらず、中小企業や個人事業主の経理業務の効率化をわかりやすく指導する専門家。中小企業の経営者が経理業務に苦戦する姿を見て、今後の中小企業の発展にはIT面からのサポートも欠かせないと考え、クラウド会計の導入やITを活用した顧問先業務の効率化を推進中。
プロフィールを見る >
インボイス のテンプレート一覧へ
インボイス制度に対応した請求書や領収書テンプレートのほか、取引先の登録番号を管理するシートや通知文等、Excel(エクセル)形式やWord(ワード)形式の様々なテンプレートが無料でダウンロードできます。
インボイス制度に関する解説記事と合わせてご利用ください。