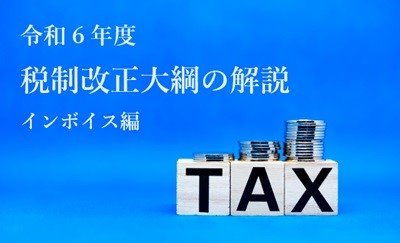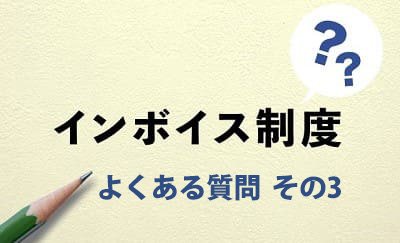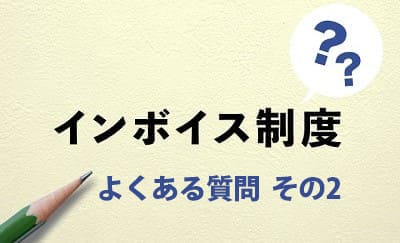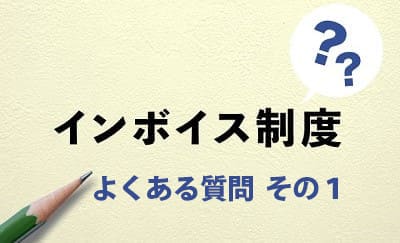加藤 博己 さんの執筆/監修記事一覧
作者・監修者プロフィール
- 作者名
- 加藤 博己
- 会社/事務所名
- 加藤博己税理士事務所 所長
- 肩書き
- 税理士
- 専門分野
- 税務、会計、中小零細企業へのITサポート
- 強み
- ・税理士でありながら、税理士という枠にとどまらず、中小企業や個人事業主の経理業務の効率化をわかりやすく指導する専門家。
・事務所ホームページ内のブログにおいて、効率化のアイデアやITツールの使い方などについて発信するなど、主に小さな会社の情報格差(デジタルディバイド)解消への取組みにも強みを持つ。
- 経歴
- ・大学卒業後に入社したパナソニックにて約19年間経理業務および経営管理業務を幅広く担当。30代のうち7年間を欧州で勤務。
・40歳のときに、これまで身につけてきたスキルを大きな組織の中ではなく、中小企業の経営改善に直接役立てる仕事をしたいと考え会社を退職。その後3年で税理士資格を取得。
・中小企業の経営者が経理業務に苦戦する姿を見て、今後の中小企業の発展には税務・会計にとどまらずIT面からのサポートも欠かせないと考え、クラウド会計の導入やITを活用した顧問先業務の効率化を推進中。
- 資格
- 税理士、AFP、二級ファイナンシャル・プランニング技能士、弥生認定経営支援アドバイザー、freee認定アドバイザー、MFクラウド会計認定アドバイザー
- 営業エリア
- 京都府・滋賀県・奈良県・大阪府(京都市内から片道1.5時間以内のエリア)
※上記以外のエリアでもオンラインにて対応しますのでご相談ください
加藤 博己さんの執筆/監修記事一覧
インボイス制度に対応するため事業者登録をして、初めて消費税申告書を作成することになった個人事業者の方へ。2割特例を適用して申告書を作成する際に注意するべきポイントを解説します。
2023年12月に公表された令和6年度税制改正大綱のうち、インボイス制度に関連する内容について、経理実務にも影響する点を中心に解説します。
電子帳簿保存法により、2024年1月から、PDFなど電子データで受け取った請求書等の書類はデータ保存することが義務化されます。その際に必須となるのが「改ざん防止」対策ですが、その手段のひとつ「事務処理規程の備付け」について解説します。
電子帳簿保存法により、いよいよ2024年1月から「データで受け取った請求書などはデータのまま保存」することが必要になります。 本記事では、電帳法で定められた要件を確認しながら、その保存方法について解説します。
インボイス制度に関する実務上のよくある質問 その3
インボイス制度に関する実務上の悩みや疑問について、売手・買手それぞれの立場から取り上げて税理士が回答する「よくある質問」第3弾です。
インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者となった個人事業者の方へ。確定申告に向け、気をつけるべき点について解説します。
インボイス制度に対応するなかで「こういった場合はどうすればいいの?」と迷った時にチェックしていただきたい「よくある質問」第2弾です。
インボイス制度が始まりましたが、実務の中で「こういった場合はどうすればいいの?」という疑問がいろいろと出てくるかもしれません。そこで、インボイスに関する「よくある質問」を取り上げ、解説します。
インボイス制度が始まると「インボイス」と「インボイス以外の請求書等」で仕入税額控除の扱いが変わります。経理処理がどう変わるのか、また注意すべき点について解説します。
インボイス発行事業者の登録申請はしたものの、10月1日までに登録番号の通知が間に合わない…という場合の対処方法について解説します。