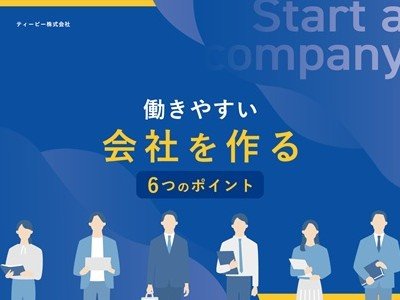テレワーク導入の方法・メリット・必要な準備|課題や注意点も解説
最終更新日:2025年06月05日

この記事では、テレワークの種類やメリット・デメリットを整理し、導入プロセスを具体的なステップに分けて解説します。また、成功のための運用ポイントや実例も交えて、効果的なテレワーク環境を構築するためのヒントをご紹介します。
テレワーク導入を検討している方は、ぜひ本記事を参考にして、自社の課題や目的に合った最適な働き方を実現してください。
【おすすめ資料】
働きやすい会社を作る6つのポイント
- テレワークとは
- テレワークの種類
- 自宅利用型(在宅勤務)
- 施設利用型
- モバイルワーク
- ワーケーション
- テレワーク導入のメリット
- 優秀な人材の確保
- 生産性の向上
- 固定費の削減
- 従業員の幸福度向上
- テレワーク導入の方法と必要な準備
- 人事評価制度の整備
- 勤怠管理制度の整備
- コミュニケーション手段・機会の確保
- 情報セキュリティ管理
- 必要な機器の確保
- テレワーク導入における課題・注意点
- テレワークに適さない・できない業務の存在
- 企業全体の意識改革の必要性
- 導入効果の検証と定期的な改善
- まとめ
テレワークとは
テレワークとは、ICT(情報通信技術)を活用して、時間や場所にとらわれず柔軟に働くことを意味します。もともとは働き方改革の一環として導入が推奨されていましたが、新型コロナウイルス感染防止策の一環として急速に普及しました。なおテレワークは、「離れた場所」を意味する「tele」と、「働く」を意味する「work」を組み合わせた造語です。
テレワークにはさまざまな形態があり、自宅で仕事をする「自宅利用型」、サテライトオフィスを利用する「施設利用型」、モバイルデバイスを用いてどこでも仕事ができる「モバイルワーク」、およびそれらの組み合わせなどが含まれます。テレワークは、場所にとらわれない働き方を実現しつつ、人と人との接触を減らし、感染症の拡大を防ぐ有力な手段としても注目されています。
テレワークの種類
最近ではテレワークが急速に広まり、上述したようにさまざまな形態が登場しています。それぞれに独自のメリットとデメリットがあります。この異なるテレワークの種類について、もう少し詳しく探ってみましょう。
自宅利用型(在宅勤務)
自宅利用型は、自宅にインターネット環境を整え、ICTツールを活用して業務を進める働き方です。このスタイルでは、メールやチャット、Web会議システム、電話、FAX、勤怠管理システムなどを活用して遠隔勤務をサポートします。通勤時間を削減できるため、育休明けの時短勤務と組み合わせることで、家庭と仕事の両立がしやすくなる点が大きな魅力です。
また、オフィスに出勤したり、顧客への訪問や会議参加などにより外出したりすることがなく、基本的に一日の業務をすべて自宅の執務環境の中でおこないます。これにより、通勤負担が軽減され、時間を有効に活用できます。企業によっては、全日程を在宅勤務とせず、週に数日だけ在宅勤務を推奨するケースもあります。
このスタイルは、従業員のワーク・ライフ・バランスを実現する上で効果的です。育児や介護の期間中でも従業員がキャリアを継続でき、障がいなどで通勤が困難な従業員の就労継続にも有効です。さらに、静かな環境を整えやすく、集中して業務をおこなえます。
施設利用型
施設利用型は、シェアオフィスやサテライトオフィス、コワーキングスペースなどを活用する働き方を指します。企業は、Wi-Fiなどが整ったこれらの施設を利用することで、従業員が快適かつ効率的に作業できる環境を提供します。
特に、在宅勤務よりも整った作業環境であることが特徴です。企業は単独でサテライトオフィスを設置することもありますが、費用や管理面での負担を軽減するために、シェアスペースを契約して従業員に利用させるケースも増えています。こうしたオフィスは地方創生の一環として、都心企業が郊外や地方に設置する例も見られます。
モバイルワーク
モバイルワークは、オフィス以外の場所でも効率的に働ける方法です。パソコンやスマートフォンを使い、新幹線や飛行機、カフェ、顧客先などで業務をおこないます。この働き方は移動中や隙間時間を有効活用できるため、業務の効率化につながります。
また、モバイル通信を利用するため、自宅にWi-Fi環境がなくても問題ありません。営業職など外出が多い業務に特に適しており、直行・直帰を活用することでワーク・ライフ・バランスの向上も期待できます。
ワーケーション
ワーケーションとは、リゾート地や観光地などの休暇先で、ICTを活用して仕事をする働き方です。この言葉は「働く」を意味する「work」と、「休暇」を意味する「vacation」を組み合わせた造語で、2000年頃にアメリカで生まれました。
日本では新型コロナウイルスの影響で政府が推進し、注目を集めました。非日常の環境での就労は、業務ストレスの緩和や健康的な働き方を実現し、地域貢献にもつながるとして人気が高まっています。
テレワーク導入のメリット
テレワークの導入は、企業に多くのメリットをもたらします。テレワークの主なメリットとしては、以下のようなものが挙げられます。
優秀な人材の確保
企業が優秀な人材を確保するためには、テレワークの導入が有効です。柔軟な働き方を実現することで、社員のライフスタイルが変化しても対応でき、長く働ける環境を整えられます。
たとえば、結婚や出産、介護などの理由で従来の勤務形態を続けるのが難しい場合でも、テレワークを活用することで継続して働けます。これにより、人材の流出を防ぎ、人手不足の解消や採用コストの削減にもつながります。
またテレワークは、通勤のストレスや時間のロスが減るため、従業員のモチベーション向上や優秀な人材の採用にも寄与します。企業がテレワークを積極的に導入する姿勢は、求職者にとっても魅力的であり、競争力を高める要因となります。
生産性の向上
テレワークを導入することで、従業員の生産性が向上する可能性があります。その主な理由の一つは、通勤時間が不要になる点です。通勤に費やしていた時間を、スキル向上や自己管理のための時間として有効に活用できるようになります。また、通勤によるストレスが軽減されることも大きな要素です。ラッシュアワーの混雑や移動の疲れがなくなることで、従業員はよりリラックスした状態で業務に取り組むことが可能になります。その結果、業務への意欲やモチベーションが向上し、効率的に仕事を進めることが期待されます。
固定費の削減
固定費の削減には、テレワークの導入が効果的です。社員の通勤が不要となり、交通費の支給を削減できます。また、オフィススペースを縮小することで、家賃や光熱費を抑えることが可能です。
一部の企業では、本社を家賃の安い地方に移転し、さらに固定費を削減しています。たとえば、ある企業は本社機能の一部を淡路島に移転し、多くの社員が引っ越した結果、家賃負担を軽減しました。加えて、会議や出張の減少により、交通費も大幅に削減されています。
従業員の幸福度向上
テレワークの導入は、従業員の幸福度向上にも寄与します。通勤や勤務場所に縛られることがなくなれば、家族とのコミュニケーションの時間が取れたり、運動や趣味に充てられる時間を増やしたりできます。その結果、プライベート時間の充実やストレスの軽減により、幸福感の向上につながります。
一方で、従業員同士の交流機会が減るため、その対策も必要です。テレワークは、仕事のペースを自分で調整できるため、職場での幸福度を高め、企業に対する忠誠心を強化する可能性があります。
テレワーク導入の方法と必要な準備
テレワークの導入は、現代の働き方改革を支える重要なステップであり、企業にとって柔軟な働き方を実現する鍵となります。ここでは、その方法と必要な準備について詳しく解説します。
人事評価制度の整備
テレワークを導入する場合、従来の評価制度では公平な評価が困難になる可能性があります。そのため、長期的な視点での評価制度の見直しが必要です。
新しい評価制度を定める際は、社員への周知・理解・意識改革が重要であり、オフィス勤務者への配慮も求められます。労働時間管理の問題から、テレワーク規定の制定も必要です。
また、評価方法にばらつきが生じないよう、統一的な評価基準の策定も欠かせません。評価プロセスの停滞を防ぐためにも、適切なコミュニケーション手段の確保が求められます。
勤怠管理制度の整備
テレワークにおいては、社員を直接的に管理することが難しく、また社員側としても業務に常に集中することが求められます。そのため、テレワークに最適な勤怠管理システムや制度の導入が重要です。
自宅が作業場となる場合、勤務時間の区切りが曖昧になることが多いため、全社的にシステムで勤務時間を明確に把握する必要があります。パソコンやスマホで打刻可能な勤怠管理システムを活用し、自社に合ったスタイルを選択することが求められます。
コミュニケーション手段・機会の確保
テレワークにおいてはコミュニケーションの減少が懸念されるため、コミュニケーションツールの導入が重要です。たとえば、チャットはメールより手軽で誤送信リスクが低く、形式的な挨拶なしに迅速なコミュニケーションが可能です。また、スケジュール管理機能付きツールは、メンバーの状況把握に役立ちます。
そのほか、ビデオ通話やWeb会議システムは、表情や細かなニュアンスの伝達を容易にし、不安の解消にも貢献します。適切なツールの導入で、遠隔でも生産性とチームの結束力を維持できます。
情報セキュリティ管理
テレワークでは、重要な情報を社外で扱う機会が増えるため、情報セキュリティ対策が求められます。会社は情報管理のガイドラインを作成し、ウイルス対策ソフトの提供や、社外環境からの安全なアクセス手段の整備といった対応が必要です。
また、従業員も情報の管理方法について意識を高め、紛失や情報漏洩に注意しなければなりません。定期的に研修やチェックテストを実施し、セキュリティ意識を持続させることが効果的です。
必要な機器の確保
テレワークを実施する際、使用するパソコンの選定は重要です。社有パソコンの貸与、新たに支給、または私用パソコンの利用(BYOD)により、費用が大きく異なります。
特に、個人デバイスの利用にはセキュリティリスクが伴います。OSの最新アップデートやウイルス対策ソフトの未インストールは、マルウェア感染の原因となり、機密情報の漏洩リスクも増大します。会社で許可されたデバイスの使用や、運用ルールの徹底が求められます。業務開始日までに必要なデバイスを準備してください。
テレワーク導入における課題・注意点
テレワークの導入は、生産性の向上やコスト削減といったメリットが期待できる一方で、いくつか注意すべき点もあります。これらの注意点に留意することで、テレワークの利点を最大限に活用できます。
テレワークに適さない・できない業務の存在
エッセンシャルワークや機密情報を扱う業務、紙ベースやハンコが必要な業務など、一部の職種や仕事内容ではテレワークが難しい場合があります。たとえば、電話応対やFAX確認、契約書や稟議書への押印などはテレワークでは対応が困難です。
また、稟議書や請求書の取り扱いがある業務は、紙書類の管理と印鑑の捺印がネックとなり、テレワークには不向きです。一方、人事、経理、総務などの業務はテレワークに適していますが、紙の書類がある場合には運用方法の見直しが要検討です。
このように、テレワークの導入には職種や仕事内容に応じた精査と対策が求められます。また、テレワークができる・できないことにより不公平感が生じる可能性もあるため、十分な配慮が求められます。
企業全体の意識改革の必要性
テレワークの定着には、経営層・社員を問わず、企業全体での意識改革が欠かせません。経営陣が率先して新しいルールを実践し、オンライン会議への切り替えやテレワークマネジメント教育を推進することが重要です。評価体制も客観的に見直し、社員が納得できる形でのツール導入が求められます。
また、社員とよく話し合い、目標や評価項目を明確にしておくことが必要です。テレワーク導入の意義を理解し、経営層自ら情報発信をおこなうことで、従業員の意識改革を進められます。そのためには、説明会の開催や、従業員からの要望を反映した規則の作成と周知が重要です。
導入効果の検証と定期的な改善
環境や制度を整え、テレワークを導入しても、運用中に課題が生じる可能性があります。そのため、量的評価と質的評価の2つの基準を用いて効果を検証することが重要です。たとえば、コスト削減が達成できた場合は、量的に評価が高いといえます。一方、コミュニケーションの円滑さや顧客からのフィードバックは質的評価に該当します。
また、従業員へのアンケートを実施し、テレワークに対する受け止めを確認することも欠かせません。定期的な状況把握を通じて、労務管理や人材育成の制度を改善し、テレワークの課題に対応していきましょう。
まとめ
テレワークは、パソコンやスマートフォンを活用し、オフィス外で働く方法です。自宅で仕事をする「自宅利用型」、会社から離れた場所で仕事をする「施設利用型」や「モバイルワーク」、仕事と休暇を組み合わせた「ワーケーション」など、さまざまな働き方があります。
企業にとっては、優秀な人材を確保しやすく、社員の満足度を高められる点がメリットです。また、オフィスにかかる費用の削減や、生産性向上も期待できます。
しかし、すべての仕事がテレワークに適しているわけではありません。情報漏洩のリスクや、チームワークが低下する可能性など、注意すべき点もあります。そのため、テレワークを導入する際には、事前にしっかりと準備することが重要です。
●課題解決に役立つ資料のダウンロードはこちらから
働きやすい会社を作る6つのポイント