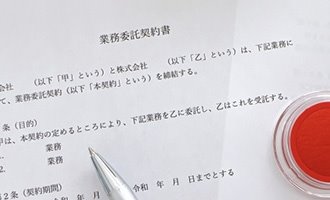フリーランス新法で押さえるべきポイントと契約書の注意点を徹底解説!
最終更新日:2024年11月14日

これまでも「下請法」との関係で「業務委託契約書」等の整備をおこなってきた企業もあるでしょうが、このたびの新法は「下請法」に比べて対象となる企業、取引の範囲が広くなりますので、要チェックです。
「フリーランス新法」でいうところの「フリーランス」との対象取引に対しては、事業規模や資本金規模に関係なく「フリーランス新法」が適用になります。
自社内に法務の専門部署があるか、もしくは契約書に精通した人材がいればよいのですが、そうでない場合、対応の必要があるのかどうか、どのように対応したらよいか、迷われるかもしれません。
そこで、今回のコラムでは「フリーランス新法」でおさえるべき「契約書」のポイントと注意点を中心にその内容を整理し、徹底解説をいたします。
- そもそもフリーランス新法(フリーランス保護新法)とは?
- フリーランス新法制定の背景とよくある取引先とのトラブル
- フリーランス新法施行後に業務委託契約書を作成する際の注意点
- フリーランス新法に違反した場合の制裁は?
- まとめ
そもそもフリーランス新法(フリーランス保護新法)とは?
働き方の多様化が進むにつれて「フリーランス」人口も増えつつあります。
企業側のアウトソーシングニーズとも合致して、フリーランスへ業務委託するケースは増え続けています。
一方で、フリーランスの方々は委託側事業主との取引関係上、立場が弱くなるケースが多く、報酬の支払い関係で不利な条件を強いられたり、厳しい労働環境に置かれるといった問題がありました。
これまでも、フリーランスが安心して働ける環境を整備することを目的として「フリーランスガイドライン」が策定されるなど、フリーランスを保護する施策は進められてきました。しかし、ガイドラインでは「取引の適正化」や「就業環境の整備」といった点において不十分な部分がありました。
このたび「立法」という形となり、強制力を持たせたことは大きな前進であり、発注事業者側も法に則った対応を取る必要があります。
(1)発注事業者の定義とは?
それでは、「フリーランス新法」の適用対象となる「発注事業者側」の「定義」から確認していきましょう。
「フリーランス」に対して「業務を委託」する側の『事業者』は、基本的には「フリーランス新法」の適用対象となる「発注事業者」になります。
ただし、「従業員の使用」によって下記の2つの「発注事業者」に分けられます。
・「特定業務委託事業者」 ⇒従業員を使用する事業者
・「業務委託事業者」 ⇒従業員の使用の有無を問わない事業者
ちなみに、自身がフリーランスであってもフリーランスに対して業務を委託するのであれば、「フリーランス新法」の「発注事業者」となりますのでご注意ください。
(2)フリーランス新法におけるフリーランスの定義と対象者について
つづいて、フリーランス新法における「フリーランス」の定義はどのようになっているのでしょうか?
この法律でいうところの「フリーランス」の「定義」は、
「業務委託先であって、従業員を使用しないもの」ということになります。
具体的には…
・企業に属さず個人で働く人
・一人社長会社のような従業員がいない法人
・建設業界の一人親方と言われるような職人
といった形態で働く方々です。
※ちなみに、年齢制限や業種・業界の制限もありません!
一般的には、「フリーランス」の定義として「従業員を使用している個人事業主の方」も含まれていると思われるかもしれませんが、そのような個人事業主の方は「フリーランス新法」が保護対象としている「フリーランス」の定義・対象には含まれないことにも注意が必要です。
また、一般消費者との取引にもフリーランス新法の適用はありません。
フリーランス新法制定の背景とよくある取引先とのトラブル
先に述べたように「フリーランス新法」の制定背景には、フリーランスとの取引におけるトラブル・問題から「フリーランス」を保護する目的があります。
「フリーランス新法」の内容を制定するにあたって、具体的にはどのようなトラブルが問題となってきたか確認していきましょう。
【トラブル事例1】
「取引の条件や内容があいまいで、契約書等に明確に表示されていない!」
「取引に際して契約書を作成・交付してくれない!」
「当初契約の報酬額から、一方的な都合で報酬を減額要求された!」
「納品が完了しているのになかなか報酬を支払ってもらえない!」
「報酬の支払期日が3か月以上先の契約とされて困っている!」
などといった、発注事業者側のフリーランスに対する強硬的な取引や取引内容の変更など、発注事業者側の強い立場を利用したフリーランスの利益を害する不適切な行為によるトラブルが後を絶ちません。
【トラブル事例2】
業務の募集を出す際の広告等で「虚偽の表示」や「誤解を招くような表現」が用いられており、実際の業務委託の内容と違っていた等のトラブルもよくあるケースです。
業務の募集をおこなう際の広告等では、そのような虚偽内容は言うまでもなく、誤解を招くことのないように「正確」で「最新の情報」を保つようにしなければなりません。
【トラブル事例3】
委託を受けた業務先での「セクハラ・マタハラ・パワハラ」などのハラスメントにより、フリーランスの就業環境が厳しい状況下にあるケースも問題視されてきました。
「フリーランス」は「雇用契約」ではないため、労働基準法による保護がありません。
立場の弱いフリーランスに対するハラスメントのトラブル事例は後を絶たない状況となっていました。
こうした劣悪な就業環境からの保護は、下請法にはない「フリーランス新法」特有の規定となっており、ハラスメントによるトラブルを回避させる効果が期待されます。
フリーランス新法施行後に業務委託契約書を作成する際の注意点
「フリーランス新法」の対象となる「業務委託契約書」における注意点は、「取引の適正化」による「義務や禁止事項」への対応や「就業環境の整備」への対応として盛り込むべき条項がポイントです。
ここでは、具体的な条項例を示して「フリーランス新法」における注意点を解説します。
《問題のある条項例1(取引条件の明示)》
《修正ポイント》
「フリーランス新法」では「取引条件の明示義務」があります。
上記の条項のように、契約書等の書面により「取引条件の明示」がなされていない
契約は、「フリーランス新法」に違反することになるため注意が必要です。
「本件業務の詳細及び具体的遂行方法は、別紙のとおりとする。」といった条項内容にしたうえで「別紙」にて「取引条件の明示」をする方法でもかまいませんので、法律に定められている「9つの明示事項」を契約書等の書面またはメールなどの電磁的記録でフリーランスに対してしっかりと明示しましょう。
《問題のある契約条項例2(報酬の支払いについて)》
《修正ポイント》
「フリーランス新法」では、甲が「特定業務委託事業者(従業員等がいる事業者)」である場合、支払期日は成果物の受領又は役務の提供を受けた日から60日以内のできる限り短い日に設定しなくてはなりません。
上記の条項例ですと、役務の提供を受けた日から60日以内の支払い義務を果たせない可能性があります。支払日が必ず60日以内となるように修正が必要です。
《問題のある契約条項例3(禁止行為の事例1:受領拒否・返品)》
《修正ポイント》
「フリーランス新法」では、甲が「特定業務委託事業者(従業員等がいる事業者)」で1か月以上の業務委託契約をしている場合には、7つの禁止行為が適用されます。
「受領拒否」や「返品」といった行為は禁止行為に該当するため、上記のような内容を契約に含めることはできません。
その他にも、「報酬の減額」「買いたたき」といった行為も禁止されていますので、
・報酬を支払うときに手数料を差し引いて支払う行為
・原材料高騰などのコスト増があるにもかかわらず、フリーランスと協議せず報酬額を維持して発注しつづけている
などといった行為も「フリーランス新法」における「禁止行為」に該当する恐れがありますので注意が必要です。
《問題のある条項例4(禁止行為の事例2:購入・利用強制)》
《修正ポイント》
「フリーランス新法」では、甲が「特定業務委託事業者(従業員等がいる事業者)」で1か月以上の業務委託契約をしている場合には、7つの禁止行為が適用されます。
「購入・利用強制」といった内容は発注事業者側の立場を利用した不当な契約内容となるため、上記の条項例のように業務委託をするにあたって甲の都合による強制的な「購入」や「利用させること」を含めた契約内容にすることは禁止されています。
《問題のある条項例5(禁止行為の事例3:不当な経済上の利益の提供要請)》
《修正ポイント》
「フリーランス新法」では、甲が「特定業務委託事業者(従業員等がいる事業者)」である場合で1か月以上の業務委託契約をしている場合には、7つの禁止行為が適用されます。
発注事業者側の立場を利用した、フリーランスにとって不利益となる「金銭」や「労務」の提供をさせる行為は「不当な経済上の利益の提供要請」にあたる契約内容となります。そのため、現場の指示で契約業務外の労務を無償で提供するように指示をすることは禁止されています。
また、「納品後に追加費用なしで、やり直しや給付内容の変更、既に作業した分の費用などを払わずに発注取消」を強いることは、フリーランスの利益を不当に害する行為となり「不当な給付内容の変更・やり直しの禁止」に該当する恐れがあるので注意しましょう。
《問題のある条項例6(更新の拒絶)》
《修正ポイント》
「フリーランス新法」では、甲が「特定業務委託事業者(従業員等がいる事業者)」で6か月以上の業務委託契約をしている場合には、「更新の拒絶」をする際、少なくとも30日前までに「書面」「ファクシミリ」「メール」等にて「更新しない旨」を予告しなければなりません。
上記の条項例のように予告期間が短い場合には「フリーランス新法」に違反する契約内容となるため注意が必要です。
《問題のある条項例7(契約解除の予告)》
《修正ポイント》
「フリーランス新法」では、甲が「特定業務委託事業者(従業員等がいる事業者)」で6か月以上の業務委託契約をしている場合、「契約を中途解除」をする際には、「更新拒絶」と同様に少なくとも30日前までに「書面」「ファクシミリ」「メール」等にて「更新しない旨」を予告しなければなりません。
上記の条項例のように予告期間が短い場合には「フリーランス新法」に違反する契約内容となるため注意が必要です。
《問題のある条項例8(中途解約の理由開示)》
前の2事例のように「更新拒絶」や「中途解除」の義務を負っている場合、予告がされた日から契約が終了する日までの期間にフリーランスから「更新拒絶や中途解除の理由の開示」を請求された際には、「同様の方法により、遅滞なく開示しなくてはならない」ことが義務付けられています。
上記の条項例のような「開示義務を負わない」といった内容は「フリーランス新法」に違反する契約となりますので注意が必要です。
《入れておいた方がよい条項例1(ハラスメント対策に係る体制整備)》
- 甲(発注事業者)は、各種ハラスメント対応のための体制整備その他必要な措置を講じるものとする。
- 乙(フリーランス)は、各種ハラスメントの相談先として以下の窓口を利用することができるものとする。
【窓口名/担当者名】
【連絡先】
【電子メールアドレス】 - 甲は、乙がハラスメントに関する相談を行ったことを理由として不利益な取扱いを行わないことを乙に対し表明し、保証する。
「フリーランス新法」では「就業環境の整備」も義務付けされているため、契約書には上記の条項例のような「ハラスメント対策に係る体制整備」に関する内容も盛り込み、ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されないよう必要な措置を行っていることを明示したほうがよいでしょう。
《入れておいた方がよい条項例2(育児介護等の業務の両立に関する配慮義務)》
- 乙(フリーランス)は、甲(発注事業者)に対し妊娠、出産、育児又は介護(以下「育児介護等」という)と本業務の両立に関する配慮申立てを行うことができるものとする。
- 甲は、前項に定める申立てがなされた場合、育児介護等と本業務が両立できるよう乙の育児介護等状況に応じ必要な配慮を行うものとする。
「フリーランス新法」では、6か月以上の業務委託契約をしている場合には「フリーランスの申出に応じて育児介護と業務との両立ができるように必要な配慮」をする「義務」があり、6か月未満の業務委託契約の場合でも「努力義務」があります。
契約書には、上記の条項例のような「業務との両立への配慮」を行っている旨の内容を明示したほうがよいでしょう。
《入れておいた方がよい条項例3(適用範囲の確認のため)》
「フリーランス新法」における「フリーランス(特定受託事業者)」の定義は、本コラムの最初の方でも説明した通り、「従業員等がいない」ことが条件になります。
契約当時は「フリーランス新法」における「フリーランス」に該当していた場合でも、契約期間中に従業員を雇い入れる等して、「フリーランス新法」における「フリーランス」の定義から外れることになるケースが想定されます。
したがって、上記の条項例のように「適用範囲の確認のため」の条項を盛り込み、「適用範囲」を明確にしておくとよいでしょう。
フリーランス新法に違反した場合の制裁は?
「フリーランス新法」の罰則規定ですが、発注事業者が違反したことがわかった場合には行政の調査を受けることになり、「指導・助言」や「必要な措置を取ることを勧告」されます。
もし勧告に従わなければ「命令・企業名公表等」になり、さらに、命令違反、義務となっている報告の不履行、検査拒否などがあれば「50万円以下の罰金」が科されることもあります。
まとめ
「フリーランス新法」の施行により、その影響を受ける事業者は相当数になるかと思います。
よって、「契約書整備」や「就業環境の整備」といった「フリーランス新法」への対応準備・対策が必要となる事業者は下請法の比ではないでしょう。
対策を講じるにあたっては、「新法の対象範囲」への理解と整理がまず必要ではないでしょうか。
今回のコラムでは「フリーランス新法」の概要を整理し、実際に「業務委託契約書」を作成・修正する際の具体的な事例解説まで内容を広げて展開しました。
今回の内容を参考にしていただくことで、フリーランスで働く方々の保護とともに、発注事業者側の発展へも寄与できますことを願っております。
執筆者情報
エニィタイム行政書士事務所 代表 中村 充(行政書士)早稲田大学商学部卒業後大手通信会社に入社、法人営業や法務業務に携わる。2009年に行政書士資格を取得し、2017年、会社設立及び契約書作成に特化した事務所を開業。弁護士・司法書士・税理士・社会保険労務士等各種専門家との連携体制を構築し、企業活動のバックオフィス業務すべてのことをワンストップで対応できることも強み。
プロフィールを見る >
関連記事
業務委託契約書 のテンプレート一覧へ
業務委託契約書は、業務を外部に委託する場合に、委託内容や期日・契約期間、報酬、秘密保持などの契約内容を明記し、委託者と受託者の間で取り交わすものです。
業務内容や取引条件を明文化することにより、双方が共通認識を持ち、トラブルを防止することができます。
業務委託契約には「請負契約」「委任契約」「準委任契約」の3タイプがあります(準委任契約は委任契約の一種ですので「委任契約」と記載されることもあります)。
ソフトウェア開発やデザイン制作、建設工事など、仕事の完成を目的とし、成果物の完成・引き渡しをもって報酬が支払われるものを「請負契約」と言います。
一方、業務の遂行を目的とし、成果物ではなく業務の遂行そのものに対して報酬が支払われるものを「委任契約」と言います。そのうち、訴訟や契約交渉など法律行為を委任する場合は「委任契約」、保守・管理業務や事務処理など法律行為以外の業務を委任する場合は「準委任契約」と言います。
テンプレートBANKでは、タイプ別・委託業務別に契約書雛形をご用意していますので、取引内容に合ったものをご利用ください。
※フリーランス新法に対応した業務委託契約書も公開しました。
Word(ワード)形式のテンプレートは無料でダウンロードいただけます。