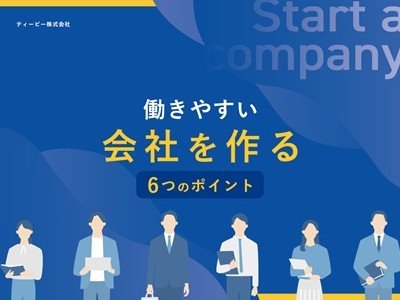フレックスタイム制のメリット・デメリット|導入手順も解説
最終更新日:2025年06月05日

【おすすめ資料】
働きやすい会社を作る6つのポイント
- フレックスタイム制とは
- フレックスタイム制の仕組み
- フレックスタイム制のメリット
- フレックスタイム制のデメリット
- 労務管理の複雑化
- クライアント対応が難しくなる可能性
- 従業員のパフォーマンス低下リスク
- 社内コミュニケーションの不足
- 経費の増加
- フレックスタイム制を導入する際の手順
- 【Q&A】フレックスタイム制に関するよくある質問
- フレックスタイム制と裁量労働制との違いは?
- フレックスタイム制と変形時間労働制との違いは?
- まとめ
フレックスタイム制とは
フレックスタイム制とは、一定期間について定められた総労働時間の範囲内で、従業員が自分で毎日の始業・就業時間を決められる制度です。
フレックスタイム制の導入により、子どもの送迎や親の介護に対応できたり、ストレスに感じる通勤ラッシュを避けたりすることが可能になります。また、自分のプライベートや趣味を大切にでき、ワーク・ライフ・バランスが充実させられます。離職を防止して定着率の向上につながるなど、企業にとってもメリットがあります。
働く人のニーズに合わせて多様な働き方が選べる社会を実現するため、働き方改革の一環として政府が推進している制度のひとつでもあります。
フレックスタイム制の仕組み
フレックスタイム制の仕組みを理解するために、「清算期間」「コアタイム」「フレキシブルタイム」といった言葉の意味を確認しましょう。
「清算期間」とは、定められた総労働時間を達成する期間です。起算日から数え、その期間中に決められた時間働く必要があります。清算期間の上限は3か月です。
清算期間については、たとえば、「清算期間は1か月間とし、毎月16日を起算日とする」「清算期間は、偶数月の1日から翌⽉末日までの2か月間とする。」などと定めます。
フレックスタイム制では、毎日の労働時間内に「コアタイム」と「フレキシブルタイム」を設定するのが一般的です。設定するかどうかは任意ですが、設定する場合は、その時間帯を労使協定で定めることになっています。
「コアタイム」とは必ず勤務しなければならない時間帯です。曜日ごとに時間帯を変更したり、1日に複数回の時間帯を設定したり、コアタイムがある日とない日を設けたり、と自由に決められます。
「フレキシブルタイム」とは、従業員が自由に勤務時間を決められる時間帯です。フレキシブルタイム中はいつでも出勤、退勤することができ、勤務の中抜けなども可能です。
「スーパーフレックスタイム制」は、コアタイムがなく、全ての時間帯がフレキシブルタイムとなります。一般的なフレックスタイム制よりさらに自由に働ける制度です。
フレックスタイム制のメリット
フレックスタイム制の導入は、従業員だけでなく企業にもメリットがあります。
- 残業時間の減少
- ワーク・ライフ・バランスの向上
- 業務効率の向上
- 優秀な人材の確保・流出防止
- 離職率の低下
上記の5つのメリットについて、詳しい説明をご覧ください。
1.残業時間の減少
フレックスタイム制は、業務内容に合わせて柔軟に働く時間を変えられるので、業務量が多いときは長時間働き、業務量が少ないときは早めに帰ることで、ムダな残業を減らせます。
ただし、従業員が自分で働く時間を管理するので、残業時間の正しい理解が必要です。フレックスタイム制では、残業時間を通常のように1日単位で考えるのではなく、清算期間内で実際に働いた労働時間から定められた労働時間(総労働時間)を引いた差を残業時間とします。
清算期間が1か月以内の場合は、週平均を40時間として計算した総労働時間を超えた部分が残業時間です。一方、清算期間が1か月を超える場合は、1か月の労働時間が週平均で50時間を超えないようにするといったルールが適用されます。そのため、週平均が40時間を超えたとしても、翌月に繰り越すことが可能です。ただし、精算期間内の週平均が50時間を超えると、超過分は残業時間として扱います。
参照:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署(5、7ページ)
2.ワーク・ライフ・バランスの向上
ワーク・ライフ・バランスとは仕事と生活の調和を指し、どちらかに偏らずに両方を充実させることを目指す概念です。フレックスタイム制の導入により、従業員それぞれの事情やライフスタイルに合った働き方ができ、ワーク・ライフ・バランスを実現させやすくなります。
子育てや介護をしながら働く従業員は、家庭とのバランスを取りながら仕事を続けることが可能です。また、プライベートを重視する従業員は、習い事や趣味などプライベートの時間を充実させることで心が満たされるなら、仕事への意欲が高まるでしょう。
3.業務効率の向上
フレックスタイム制を導入すれば、パフォーマンスを最大限発揮できる時間帯を従業員自身が選択して働けるため、業務効率が上がると考えられます。特に、クリエイティブな業務をおこなう場合には効果が上がりやすいでしょう。予定や体調に合わせて柔軟に働けるので、仕事に対するストレスが軽減しモチベーションの向上にもつながります。
4.優秀な人材の確保・流出防止
最近では、給与よりも勤務体系を重視する求職者が多くなっています。柔軟な働き方ができるフレックスタイム制を導入していることは、採用時のアピールポイントになり、他の企業と差別化を図れます。その結果、応募数の増加や優秀な人材の確保が期待でき、企業力の向上につながります。
5.離職率の低下
自分で出退勤時間を決め、大きなストレスである毎日の通勤ラッシュから解放されることで、従業員の満足度が高まり、離職率の低下が期待できます。
また、育児と仕事を両立させる共働きの従業員や、親の介護をしながら働く従業員は、今後ますます増加すると見込まれます。フレックスタイム制であれば、子どもの送迎や親のデイサービスの時間に合わせて柔軟に働けるので、育児や介護を理由にやむを得ず離職するケースを減らせるでしょう。
フレックスタイム制のデメリット
フレックスタイム制はメリットが多く魅力的な制度に感じますが、デメリットもあります。以下に挙げた5つのデメリットについて、内容を理解して対策を講じましょう。
- 労務管理の複雑化
- クライアント対応が難しくなる可能性
- 従業員のパフォーマンス低下リスク
- 社内コミュニケーションの不足
- 経費の増加
労務管理の複雑化
フレックスタイム制では個々の従業員で働く時間帯が異なり、他の人から見て勤務時間がわかりにくいため、労務管理が難しくなります。従業員自身に勤務時間を適切に管理させることが必要です。しかし、自己管理ができない従業員の場合、必要な勤務時間を満たしていなかったり、逆に長時間労働になっていたり、といった問題が生じる恐れがあります。
また、人事担当者が従業員を個別に管理しなければならず、負担が増大してしまいます。負担を軽減するために、フレックスタイム制に対応した勤怠管理システムの導入を検討しましょう。
クライアント対応が難しくなる可能性
クライアントから問い合わせがあった際に、担当者が不在ですぐに対応できないこともありえます。自社がフレックスタイム制を導入しても、クライアントが導入していないと、そのようなときに理解を得にくいかもしれません。
そのため、どの従業員でも対応できるように、日頃から情報共有をおこなうことが一層重要になります。また、クライアント対応が発生する時間が決まっている場合は、その時間をコアタイムにするのも効果的です。
従業員のパフォーマンス低下リスク
フレックスタイムのメリットのひとつに「業務効率の向上」があるとはいえ、従業員の中には自己管理が苦手な人もいます。そのような従業員の場合、時間的な自由度が高いことによりルーズな働き方が助長され、パフォーマンスが低下する恐れがあります。
また、しっかり働いている従業員が、他の従業員のルーズな働き方を見て「ずるい」と感じ、モチベーションを低下させるかもしれません。従業員の勤務時間だけではなく成果を把握して、適正な評価をおこなう仕組みを整備しましょう。
社内コミュニケーションの不足
従業員ごとに勤務時間が異なるため、従業員同士が顔を合わせる機会が減少し、コミュニケーション不足に陥ることがあります。気軽に相談できないと部署の一体感がなくなり、チームとしての生産性が低下する恐れがあるでしょう。個人としても、孤立感からモチベーションの低下を招き、離職につながることも懸念されます。
チャットツールやWeb会議システムなどを積極的に活用し、コミュニケーションの機会を増加させることが必要でしょう。
経費の増加
従業員の出勤時間が異なるため、オフィスの稼働時間が長くなり、その分光熱費が高くなることがあります。また、多くの従業員が深夜時間帯に勤務すると、割増賃金の支払いが増えてしまうでしょう。
経費の増加を抑えるために、エアコンや照明に人感センサーを導入し、ムダな電力消費を防ぐ工夫ができます。また、人件費を抑えるために、フレキシブルタイムのルールを整え、深夜の稼働時間をある程度制限することも検討するとよいでしょう。
フレックスタイム制を導入する際の手順
フレックスタイム制は、正しい手順で導入する必要があります。
- 対象者の選定
- 就業規則の見直し
- 労使協定の締結
- 運用に向けた整備
各手順の詳細について解説するので参考にしながら導入してください。
1.対象者の選定
フレックスタイム制は、職種や業務内容によって導入の可否が分かれます。業務の進捗を自己管理する、エンジニアやプログラマー、デザイナーや設計、研究職などの職種は特に適しています。一方で、従業員同士の連携が必要な職種や、取引先の都合に合わせて仕事する営業職は導入が難しいです。
また、フレックスタイム制を導入する際、最初から全従業員を対象にするのではなく、柔軟な働き方を希望する育児中や介護中の従業員など、一部の従業員から始める方法もあります。一部の部署から開始することも検討できます。
2.就業規則の見直し
フレックスタイム制を導入するなら「始業時刻・終業時刻の両方を労働者に委ねる」旨を就業規則に記載する必要があります。コアタイムやフレキシブルタイムの設定は任意であり、具体的な時間帯は労使協定で定めます。
就業規則を変更した場合は、管轄の労働基準監督署に届け出が必要です。届け出を怠ると、30万円以下の罰金を科される恐れがあるため、忘れず提出しましょう。従業員が10人未満の企業は、就業規則の作成や届け出は義務付けられてはいません。
3.労使協定の締結
導入に向けて企業と労働者の間で、以下の具体的な5つのルールを定め労使協定を締結する必要があります。
- 対象となる従業員の範囲を明確にする。
- 清算期間と起算日を定めて、1か月を超える場合は管轄の労働基準監督署に届け出る。
- 法定労働時間である週40時間の範囲内で、清算期間における総労働時間を定める。
- 清算期間の総労働時間を、労働日数で割って、基準となる1日の労働時間を計算する。
- コアタイムとフレキシブルタイムを設定する場合、開始時刻と終了時刻を設定する。
4.運用に向けた整備
フレックスタイム制に対して、「自分の思い通り自由に働ける」「残業代が出ない」と誤解している従業員もいるため、一人ひとりが正しく理解できるように従業員に周知する必要があります。「ライフスタイルに合わせてどのような働き方ができるのか」「どのような場合に残業代が出るのか」など実例を用いて説明することで、具体的にイメージできるように助けます。
フレックスタイム制の導入に伴い、勤怠管理が煩雑になることが予想されるので、管理の負担を軽減するために勤怠管理システムを導入しましょう。複雑な勤務時間の計算を自動でおこなうことができ、過重労働の防止に役立ちます。
【Q&A】フレックスタイム制に関するよくある質問
フレックスタイム制と混同しやすい制度に、「裁量労働制」と「変形労働制」があります。フレックスタイム制との違いを理解し、企業にとって最適な制度を導入しましょう。
フレックスタイム制と裁量労働制との違いは?
裁量労働制は、実際の労働時間に関わらず、あらかじめ定めた時間を労働時間とみなす制度です。時間外労働に対する残業代は原則として生じませんが、「みなし労働時間」を法定労働時間を超えた時間(1日9時間など)で設定した場合、超過した分は残業とみなされるため、割増賃金の支払いが生じます。また、法定休日や深夜時間帯に労働した際も原則として割増賃金を支払わなければなりません。
導入できる職種は限られており、業務遂行のほとんどを従業員の裁量に委ねる研究開発やプログラマーなどの専門職、企画、立案、調査などの業務をおこなう職種などです。フレックスタイム制とは異なり、働いた時間の長さではなく、働いた成果に応じて報酬が支払われるので、成果を出すために意欲的に仕事に取り組むことが期待できます。
フレックスタイム制と変形時間労働制との違いは?
変形時間労働制は、雇い主(企業)側が既定の期間内で自由に労働時間を割り振りできる制度です。繁忙期や閑散期、企業や部署全体の仕事量に応じて業務時間を調整できます。フレックスタイム制では従業員側が出退勤時間を決められるのに対し、変形労働時間制では雇い主側が決めるというのが大きな相違点です。
変形時間労働制は1週間、1か月、1年単位で設定できます。たとえば飲食店の場合は1週間単位で設定し、忙しくなる週末は長く勤務し、平日は短時間の勤務に抑えるといった働き方が可能です。また、観光業であれば、1年単位で設定し、観光客が多くなる大型連休や観光シーズンと、それ以外の時期で勤務時間を調整できます。
まとめ
近年の求職者は、ライフスタイルに合わせた多様な働き方ができる企業を好む傾向があります。フレックスタイム制を導入することで、柔軟な働き方ができてワーク・ライフ・バランスを実現しやすい企業としてアピールすることが可能です。ぜひ、企業や従業員の双方にメリットがあるフレックスタイム制の導入を検討してはいかがでしょうか。
●課題解決に役立つ資料のダウンロードはこちらから
働きやすい会社を作る6つのポイント